SNSで「あの先生すごい!」と話題に
この記事の結論!
綱島均教授は、日本大学 生産工学部 機械工学科の特任教授です。
専門は鉄道工学や機械力学で、教育と研究の両面で実績を重ねています。
2025年放送の『タモリステーション』出演でも、そのわかりやすい解説が話題となりました。
学生や社会との距離を縮める教授として、今注目されています。
【25日放送】「タモリステーション」新幹線総合指令所で特別取材https://t.co/Urcm4itdtt
— ライブドアニュース (@livedoornews) April 14, 2025
JR東海全面協力のもと、所在地自体も極秘だという新幹線総合指令所の非公開エリアで、タモリがタレントとして初めて特別取材。そのほか、リニア中央新幹線の工事現場の最前線も取材する。 pic.twitter.com/qdm7xfv0ge
4月25日に放送された『タモリステーション』を観て、「あのメガネの先生、すごくわかりやすい!」と感じた方、きっと多いのではないでしょうか。
SNSでも「この先生もっと知りたい」と話題になっているのが、日本大学 生産工学部 機械工学科 特任教授・綱島均(つなしま ひとし)先生です。
専門的な話を誰にでも伝わる言葉で語るその姿に、理系が苦手だった人ですら惹き込まれたはず。
「どんな経歴?」「どんな授業をしてるの?」——この記事では、そんな声に応えるべく、綱島先生の魅力と実績を、やさしく、わかりやすくご紹介します。
綱島均教授とは?その実績と注目の理由

注目されるきっかけはテレビ出演
2025年4月25日に放送された『タモリステーション』。
その「新幹線60年物語」特集に、専門家として出演されたのが綱島教授です。
穏やかで誠実な語り口と、誰にでも分かる解説に、多くの視聴者が「もっと聞きたい」と感じたことでしょう。
教育・研究分野の中心は「鉄道工学」
綱島教授の専門は、鉄道工学・機械力学・制御工学・ヒューマンファクターなど、幅広く実社会に根ざした分野です。
現在は、日本大学 鉄道工学リサーチ・センター副センター長も務められ、研究と教育の両面で第一線に立たれています。
授業では、鉄道の安全性や制御技術など、生活にもつながる知識を学ぶことができます。
教育と研究の両立が信頼の源
日々の授業に加え、
- 鉄道の車両挙動や構造解析の研究
- 操作性評価などの人間工学的視点の導入
- 国内外の大学や企業との共同研究
といった活動も行っており、「現場で役立つ学び」を重視されているのが特徴です。
総評:実績に裏打ちされた信頼
難しいことをわかりやすく、理論と実務をバランスよく伝える。
そんな教授の姿勢が、学生や教育関係者の間で信頼を集める理由なのだと思います。
綱島均教授のキャリアと受賞歴:専門性が光る歩み
キャリアの出発点は“現場”から
実は綱島教授、日本大学卒業後に神戸製鋼所での実務経験を経て、教育の道へ進まれた経歴をお持ちです。
現場での経験があるからこそ、授業でも「実際に使える力」を重視されているのです。
技術者から教育者へ——経験を学生に還元
企業での経験を、学生指導に活かしている綱島教授。
「ただ覚える」のではなく、「なぜそれが必要か」まで一緒に考えるスタイルに、学生も自然と引き込まれます。
正式に確認された受賞歴
数ある受賞歴の中でも、
- 日本機械学会 交通・物流部門 功績賞
- 自動車技術会 技術部門貢献賞
- 電気科学技術奨励賞
など、技術・研究への貢献が高く評価されていることがわかります。
※教育関連の賞については、現時点で公式に確認されていません。
誠実に積み重ねた信頼
一足飛びの成功ではなく、地道な実績と誠実な取り組みが現在の信頼につながっているのです。
“タモリステーション”での姿に学ぶ:社会とつながる教育者
科学を“伝える力”に変える先生
テレビを見て「難しい話もわかる気がした」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
それは綱島教授が、専門家としての知識を「相手に届く形」で発信できる力を持っているからです。
番組で語られた印象的なメッセージ
番組では、
- 鉄道技術の進化とこれから
- 安全性と快適性を両立させる技術の工夫
- 科学が社会を支えるという視点
などについて、丁寧かつ熱意をもって話されていました。
SNSでも話題に
放送後には、
- 「こんな先生が学校にいたら理系が好きになってた」
- 「子どもと一緒に観て良かった」
といったコメントがX(旧Twitter)を中心に広がりました。
社会と教育をつなぐ存在
テレビという“教室の外”でも、人々に学びの楽しさを届ける。
それができる数少ない教授のひとりだと感じました。
授業で見える素顔:学生と共に成長する先生
一緒に考える授業スタイル
「わからないことがあっても、先生と話せば“なるほど”に変わる」
学生からはそんな声も聞かれる綱島教授の授業。
- 鉄道のシステムや構造についてのシミュレーション
- モデルを使った実験的アプローチ
- 日常生活とつながる人間工学の視点
など、知識が“自分ごと”になる瞬間を大事にされています。
ゼミでは対話が中心
学生に問いを投げかけ、一緒に考える。
そんなゼミ形式の授業では、
「教えてもらう」だけではなく「自分で答えを出す」経験ができます。
学生の声:やりがいがあるから頑張れる
- 「自分の考えに向き合ってくれる先生」
- 「知識よりも“考える習慣”を教えてくれた」
といった声が印象的です。
現場を意識した授業設計
学びが“未来の仕事”にどうつながるのかを一緒に考える。
そんな授業だからこそ、綱島教授の授業には意味があります。
綱島教授から学べること:技術と社会をつなぐ学び
社会で活かせる“実践的な工学”
工学は、「社会でどう役立てるか」が大切。
綱島教授の授業では、それを肌で感じることができます。
実社会との関わりが視野を広げる
JR東海などとの共同研究にも携わる綱島教授。
学生もプロジェクトの一部に関わることがあり、「学ぶこと」と「社会とのつながり」をリアルに実感できます。
思考力を育てる授業
ただ知識を増やすだけでなく、
- 「なぜ?」と疑問を持ち
- 「どうしたら?」と考え
- 「やってみよう」と行動する
そんなサイクルを繰り返すことで、どんな職業にも活きる力が養われます。
日本大学 生産工学部 機械工学科での学び
“現場につながる教育”を大切にしているこの学科で、
綱島教授のような先生と出会えることは、大きな財産になるはずです。
まとめ:確かな実績と温かい人柄の両立
ここまで読んでくださりありがとうございます。
綱島均教授は、テレビ出演で注目を集めただけでなく、教育者・研究者として確かな歩みを続けてこられた方です。
- 日本大学 生産工学部 機械工学科の特任教授
- 鉄道工学リサーチ・センター副センター長
- 社会とのつながりを大切にする授業・研究スタイル
そのすべてが、多くの人々にとって学びやすく、共感できる姿勢につながっているのだと思います。
「教育と技術は、社会を支えるもの」——そんな想いが伝わる綱島教授。
もし「理系って難しそう」と思っていたら、きっとその印象が変わるはずです。
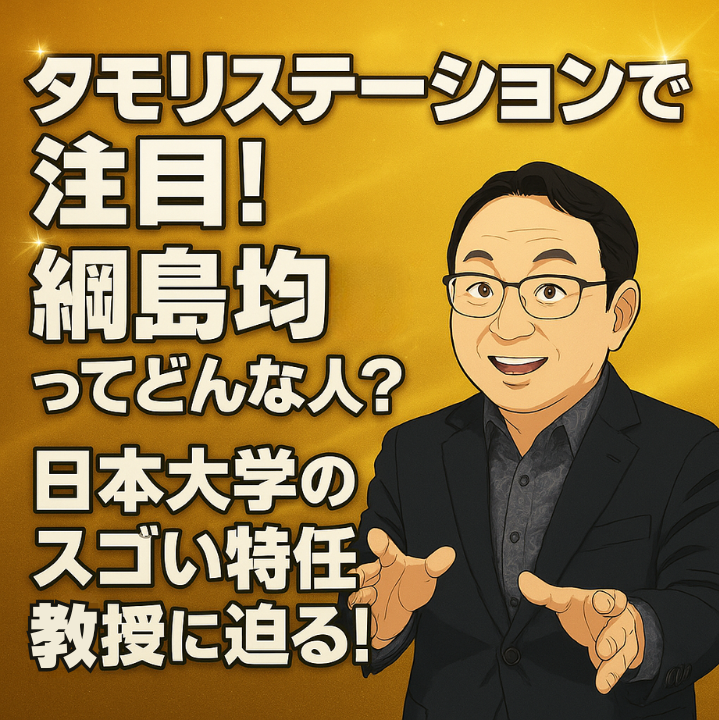
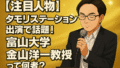

コメント