本記事は、PRを含みます。
絵を描くことが好きで、「自分もいつか絵で生きていけたら…」と感じたことはありませんか?
SNSでは毎日、美しいイラストやアニメーションが流れ、多くの人が「絵師」として活躍しています。
そんな“絵師”という存在が、いま社会的にも注目されているのをご存じでしょうか。
2025年10月7日放送の『マツコの知らない世界』では、「憧れの職業1位・絵師の世界」が特集されました。
ゲストは、YOASOBI「夜に駆ける」などのアニメーションを手がけた藍にいなさん。
彼女の言葉から、絵師として生きるリアルな世界、そして“絵で心を動かす力”が明かされます。
この記事では、番組の内容をもとに、
を、わかりやすく丁寧に解説していきます。
読み終える頃には、「絵で生きる」ことが、夢ではなく具体的な目標として見えてくるはずです。
あなたの“好き”を“仕事”に変える第一歩を、このページで踏み出しましょう。
マツコの知らない世界 絵師の世界と藍にいなの魅力を徹底解説
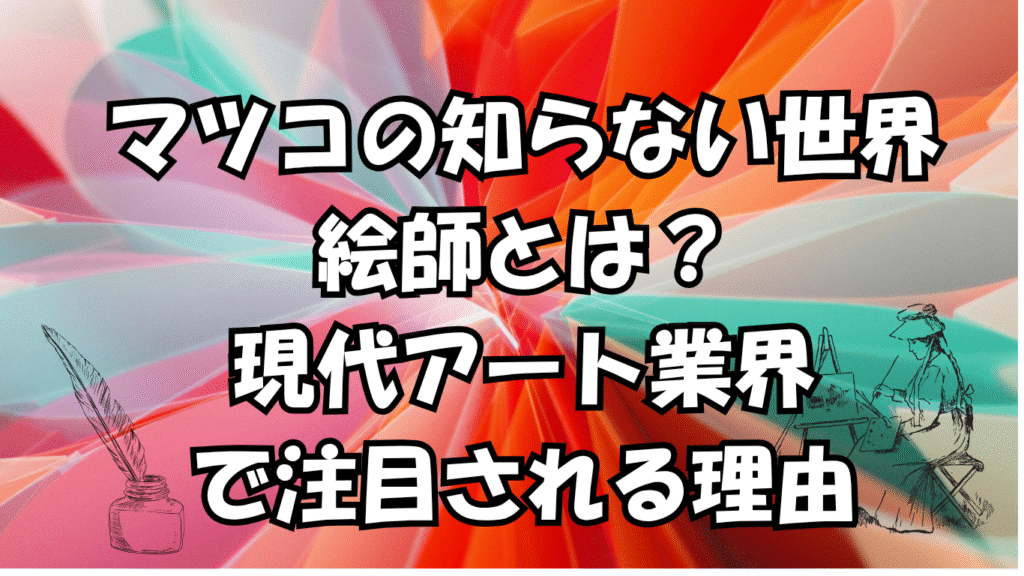
絵師とは?現代アート業界で注目される理由
「絵師」とは、単に絵を描く人ではありません。
アニメ、ゲーム、音楽、広告、SNSなど――あらゆる分野で“ビジュアルの物語”を生み出す、クリエイターの総称です。
かつてはアニメーターやイラストレーターなどの職業に分かれていましたが、近年ではデジタル技術とSNSの発達によって境界が曖昧になり、総合的に「絵師」と呼ばれるようになりました。
いま、なぜ絵師という職業がこれほどまでに注目されているのか。
その背景には3つの時代的変化があります。
- SNSによる作品発信の自由化
かつて作品を見てもらうには展示会や出版社が必要でしたが、今はX(旧Twitter)やInstagramで誰でも世界中に作品を公開できます。
「描いてアップする」だけでチャンスが広がる時代です。 - AI・デジタル技術の進化
作画アプリやタブレットの普及で、プロとアマチュアの差がどんどん縮まっています。
デジタル環境が整ったことで、個人制作でもクオリティの高いアニメーションが可能になりました。 - 企業・音楽業界からの需要拡大
MV、VTuber、ライトノベル表紙、広告デザインなど、絵が必要とされる場面が増えています。
特に「物語を感じさせる絵」が求められており、絵師の表現力が評価されています。
番組内でもマツコさんが、「こんなに“絵で食べる人”が増えてるなんて知らなかった」と驚きを見せていました。
藍にいなさんは、絵師を“誰もがなれる職業”と語っています。
「絵は学歴も資格もいらない。描くことで、自分の感じたものを伝えられる。それが仕事になるのが、いまの時代のすごさ。」
つまり、絵師とは――
“自分の世界を描き、人の心を動かす表現者”。
技術だけでなく、感情を届けることこそが求められているのです。
藍にいなが語るYOASOBI「夜に駆ける」制作秘話
【お知らせ】初のオリジナル短編アニメーションの制作にあたり、作品づくりに協力してくださる方を募集します!
— 藍にいな Ai Nina (@ainina_0211) May 3, 2025
今回は、プロダクション経験のある方、アニメーター・美術スタッフの方を中心に募集させていただきます。… pic.twitter.com/1uGyrzxwrE
YOASOBIの代表曲「夜に駆ける」。
そのミュージックビデオを初めて見たとき、静かで切ないのに、どこか心の奥に刺さる映像美に息を呑んだ人も多いでしょう。
この映像を手がけたのが、今回『マツコの知らない世界』に出演した絵師・藍にいなさんです。
番組の中で藍にいなさんは、「夜に駆ける」の制作過程を丁寧に語っていました。
彼女はまず、「絵を動かす」よりも“曲を見せる”ことを最優先に考えたといいます。
「この曲には、疾走感の中に静けさがある。その空気をどう絵で表現するか、そこにすべてをかけました。」
制作は、たった一人で行われました。
構成、キャラクターデザイン、色彩設計、撮影、編集まで、全てを自分の手で。
最初に行ったのは“歌詞の分解”。
歌詞の一行一行をノートに書き出し、
「どんな感情が動いているのか」
「この一文で何を見せたいのか」
をメモしていったそうです。
そこから生まれたのが、
映像を見返すと分かりますが、曲のリズムと感情の“呼吸”が完全に一致しています。
彼女はそれを「心のテンポ」と呼びました。
「音の波と感情の波が重なる瞬間が、いちばん“絵が歌う”とき。私はそこを逃したくないんです。」
番組中、マツコさんもこの話に深く頷きながら、
「絵って、動かなくても“動いてるように感じる”ことがあるのね」
と感嘆の声を上げていました。
また、藍にいなさんは制作中にSNSを一切見なかったそうです。
「誰かの絵を見ちゃうと、無意識に“寄せちゃう”んです。だから、曲とだけ向き合いました。」
完成後、YouTubeでの再生数は数億回を突破。
「夜に駆ける」はただのヒット曲ではなく、絵と音が一体化した新しい表現の形として語り継がれるようになりました。
彼女の語る制作秘話から伝わるのは、「描くこと=命を吹き込むこと」という信念。
マツコさんが最後に放った「あなたの絵って、“生きてる”のね」という言葉が、すべてを物語っていました。
米津玄師MVで見せたアニメーション演出の凄み
お知らせ。米津玄師さん「カナリヤ」MV内アニメーションを描かせて頂きました。
— 藍にいな Ai Nina (@ainina_0211) November 19, 2020
映像は是枝裕和監督。
素晴らしい作品の一部となることができて至極光栄です。手紙を書くような気持ちで描かせて頂きました。よろしくお願いします。
💐 (誤字していたので二度目失礼します)https://t.co/j9vTmPpMNI pic.twitter.com/nyuCp3MNjt
藍にいなさんが手がけたもう一つの代表的な仕事が、米津玄師さんのミュージックビデオ制作です。
番組では、そのアニメーション演出の緻密さと感情の深さに、マツコさんも何度も言葉を失っていました。
米津玄師さんといえば、「Lemon」「パプリカ」など、視覚と音が融合した表現に定評のあるアーティスト。
そんな米津さんの世界観を映像化するにあたり、藍にいなさんが意識したのは“静と動の余白”でした。
彼女は語ります。
「米津さんの曲って、全部が動いているようでいて、実は“止まっている瞬間”が美しいんです。
その一瞬を逃さないように、カメラを止めて“空気を感じさせる絵”を描くようにしています。」
実際、藍にいなさんが関わったMVには、他のアニメーション作品にはない独特の“呼吸”があります。
それは、画面の中で光がゆらめく瞬間や、風が吹き抜けるような無音の時間。
ほんの数秒の“止め”の中に、言葉よりも雄弁な感情が込められているのです。
マツコさんはこの映像を見ながら、
「普通は“動かす”方に意識がいくのに、あなたは“止める勇気”を持ってるのね」
とコメント。
藍にいなさんは笑いながらも、
「動かない時間って、見る人の想像力を一番信じてる瞬間なんです。」
と返しました。
さらに、彼女のアニメーションの特徴である“残響効果”も紹介されました。
これは、シーンが切り替わる直前に、前のカットの色や線を薄く残しておく演出。
視聴者の脳内に“残像”を作り出すことで、物語が継続して流れていくように感じさせる技法です。
たとえば、米津玄師さんのMVでは、登場人物が消えたあとも淡い影が残り、その影が次の風景へとつながるように演出されています。
まるで夢から覚める瞬間のような、現実と幻想のあいだに漂う美しさ――。
それが、藍にいな作品の最大の魅力なのです。
また、映像全体の色彩設計にも細やかな計算が込められています。
彼女は「米津さんの曲を“音の温度”で捉える」と語り、
この“音を色で翻訳する”感覚が、見る人の心を無意識のうちに震わせる。
音が聴覚に届く前に、絵が感情を先取りしている――
それが藍にいなさんのアニメーションの真髄なのです。
マツコさんも、
「絵なのに“音が聞こえる”ってこういうことなのね」
と感嘆。
番組の終盤では、「あなたの絵は“音楽のもう一つの形”」と語りかけました。
藍にいなさんの描く世界には、言葉を超えた“リズム”が流れています。
それは、人間の心の奥にある静かな鼓動。
見る人に「生きている」ことを思い出させる、そんな力が宿っているのです。
作品集『羽化』に込められた世界観と表現力
藍にいなさんの名をさらに広く知らしめたのが、2024年に刊行された作品集『羽化(うか)』です。
この一冊には、彼女のこれまでの代表作だけでなく、未公開のラフスケッチやコンセプトアート、そして彼女自身の想いが綴られています。
番組内では、この『羽化』の世界観と制作の裏側が丁寧に紹介され、マツコさんも「絵を超えて“人生”を感じる」と感動を隠せませんでした。
藍にいなさんがこの本に込めたテーマは、「変化」と「再生」。
彼女はこう語っています。
「“羽化”って、殻を破って新しい姿になる瞬間。
絵を描くことも同じで、描くたびに自分の古い部分を脱ぎ捨てて、少しずつ違う自分になっていく。
だからこの本は、過去の自分と今の自分が並んでいるような感覚なんです。」
ページをめくると、一貫して感じるのは“静けさの中の熱”です。
柔らかい色、淡い光、儚い線――どれも控えめで繊細なのに、目を離せない。
それは、絵の中に流れる“時間”が見えるからです。
ひとつひとつの作品に、呼吸のような間があり、まるで音楽の休符のように感情を包み込んでくれます。
藍にいなさんは、絵を描くとき「線の温度」をとても大切にしているそうです。
「線って、人の声みたいなもの。強く描けば怒りや焦り、細く震えると悲しみや迷いが出る。
一本の線が、その人の一瞬を全部語ってくれるんです。」
『羽化』では、その“線の物語”が存分に感じられます。
ページごとに登場するキャラクターたちは、誰もが何かを抱え、そして何かを手放していく。
読者の心の奥にそっと触れ、気づけば自分の過去や未来を投影してしまう。
「絵を見て泣いたのは初めて」という感想が多いのも頷けます。
さらに、マツコさんが驚いたのは、作品集の構成の美しさでした。
章立ては「繭」「羽」「風」「光」の4章構成。
繭は閉ざされた心、羽は挑戦、風は変化、光は再生を象徴しており、まるで一冊の人生譜のように物語が流れます。
中でも話題になったのが、最後のページに載っている一枚の絵。
白い羽が静かに落ちていく中、少女が空を見上げているシーンです。
その絵に添えられた短い言葉――
「痛みを知って、やっとやさしくなれた」
この一文に、多くの視聴者が心を打たれたとSNSで話題になりました。
藍にいなさんは最後にこう語っています。
「“絵”って、見た人がその続きを想像してくれた瞬間に完成すると思うんです。
この本は、私の羽化であり、見てくれた人の羽化でもあってほしい。」
『羽化』は、絵を描く人だけでなく、“自分の殻を破りたい”と願うすべての人に届く作品です。
絵師として、そしてひとりの人間として――藍にいなさんの世界は、静かに、けれど確かに羽ばたいています。
マツコが驚いた絵師のリアルな仕事現場とは
番組の中盤、マツコさんが最も驚いたのが「絵師の仕事現場のリアル」でした。
華やかに見えるSNSの投稿やMV作品の裏側には、驚くほどの努力と、地道な“職人の世界”が広がっていたのです。
藍にいなさんは、普段どんな環境で制作しているのか?
番組スタッフが密着したそのアトリエは、まるで静かな宇宙のようでした。
一面にモニターと液晶タブレット、そして壁一面にスケッチや色見本。
作業机の上には、描きかけのラフが何十枚も並び、部屋全体が“絵で呼吸している”ような空間です。
マツコさんは現場を見た瞬間、
「えっ、こんなに一人で全部やってるの!?」
と素直な驚きを漏らしました。
藍にいなさんは笑いながらこう答えます。
「一人で絵を描くって、孤独なようでいてすごくにぎやかなんです。登場人物たちが、頭の中でずっと喋ってるから。」
その言葉どおり、藍にいなさんの作業は、絵を描くだけではなく「世界を作る作業」。
1枚の絵の中に、空気の流れや音の響き、登場人物の感情の“気配”までを描き込んでいくのです。
番組では、1本のMVが完成するまでの流れも紹介されました。
合計でおよそ3〜4か月。
すべての工程を一人で担うことも多く、作業時間は1日10〜12時間に及ぶそうです。
マツコさんは思わず、「それ、もうアスリートよね…」と一言。
藍にいなさんは少し照れながら、
「でも、描いてるときは時間を忘れるんです。
気づいたら夜が明けてることも多いですけど、それがいちばん幸せな時間かもしれません。」
と微笑みました。
また、絵師の現場では、技術だけでなく「コミュニケーション能力」も重要だといいます。
クライアントとの打ち合わせや、他クリエイターとの共同制作などでは、
藍にいなさんは、「絵師って、絵を通して相手と心を交わす仕事なんです」と語っていました。
マツコさんも、「結局、絵の上手い人じゃなく、“伝えたい人”が残るのね」と感嘆。
さらに、番組では“炎上しない絵師の秘訣”にも触れられました。
藍にいなさんは、クライアントとのトラブルを防ぐために、
彼女は言います。
「絵師って自由な仕事だけど、“信頼”がないと続けられません。
納期を守るとか、約束を大切にすることが、一番の実力なんです。」
マツコさんはその言葉に大きく頷きながら、
「こういう真面目な話を聞くと、絵師って“夢”じゃなくて、ちゃんとした“仕事”なのね」
とコメント。
藍にいなさんの現場は、華やかさの裏にある圧倒的な誠実さと情熱に満ちていました。
絵師という職業のリアル――それは、“孤独と責任の中で光を描く仕事”なのです。
藍にいな流・絵師として成功するための考え方
マツコさんとの対話の中で、藍にいなさんが最も深く語ったテーマ――
それが「絵師として成功するために必要な考え方」でした。
「上手い絵を描くことよりも、“伝わる絵”を描くことのほうが大切です。」
藍にいなさんのこの一言に、マツコさんも大きく頷いていました。
藍にいなさんは、SNSの世界で何百万という人に支持されながらも、常に「見る人の心に残るものを描く」ことを意識しているといいます。
彼女の制作の根底にあるのは、“技術”よりも“共感”。
その姿勢は、アートという枠を超えて、いまを生きる多くのクリエイターに共通する哲学でもあります。
彼女は語ります。
「絵師って、“うまく描ける人”より、“誰かの気持ちを代弁できる人”のことだと思ってるんです。」
実際、藍にいなさんの絵は、どれも見る人に語りかけてきます。
泣きたい人の背中をそっと撫でるような優しさ。
誰にも言えない苦しみを抱えた人の心に寄り添う静けさ。
「描く」という行為が、まるで“祈り”のように感じられるのです。
番組内で紹介された藍にいなさんの“成功の5原則”は、多くの若い絵師志望者に響くものでした。
- 描く前に「誰のために描くか」を決める
ただ描きたいものを描くだけでは届かない。
「誰に」「どんな感情を届けたいか」を明確にすることで、絵が“メッセージ”になる。 - 完璧を目指さず、「今の自分のベスト」を出す
藍にいなさんは「未完成でもいいから、出す勇気を持つ」ことを勧めています。
完璧を求めて止まってしまうより、今描ける最高を積み重ねることが成長の近道。 - 発信を“習慣化”する
SNSに絵を投稿することは、評価を求めるためではなく、“記録”のため。
「今日の自分はここまで描けた」というログを積み重ねることで、過去の自分と比較できる。 - 他人の評価に振り回されない
「いいね」やコメントに左右されず、見る人の心に“1ミリでも届いたらそれでいい」。
藍にいなさんは、そう言い切ります。
絵は数字で測るものではなく、“残響”で感じるもの。 - 自分の“好き”を信じ抜く
流行を追うより、自分の中の“好き”を育てる。
それこそが、唯一無二の個性を生む。
マツコさんは「あなたの言葉って、ビジネス書より説得力あるわね」と笑いながらも感心。
「描くって、結局“生き方”なのね」と真剣な表情を見せていました。
藍にいなさんは最後にこう締めくくりました。
「描く理由って、最初は自分のためでいいんです。
でも、誰かが“その絵に救われた”って言ってくれた瞬間、絵は“仕事”になるんです。」
この言葉に、マツコさんはしばらく黙り込み、
「それって…人を幸せにする職業ね」と呟きました。
藍にいなさんにとって、“成功”とはフォロワー数でも賞でもありません。
誰かの心を少しでも軽くできたとき、それが最高の成功。
それこそが、“絵師”という生き方の本質なのです。
- マツコの知らない世界 絵師の世界が描く時代の変化と未来
マツコの知らない世界 絵師の世界が描く時代の変化と未来
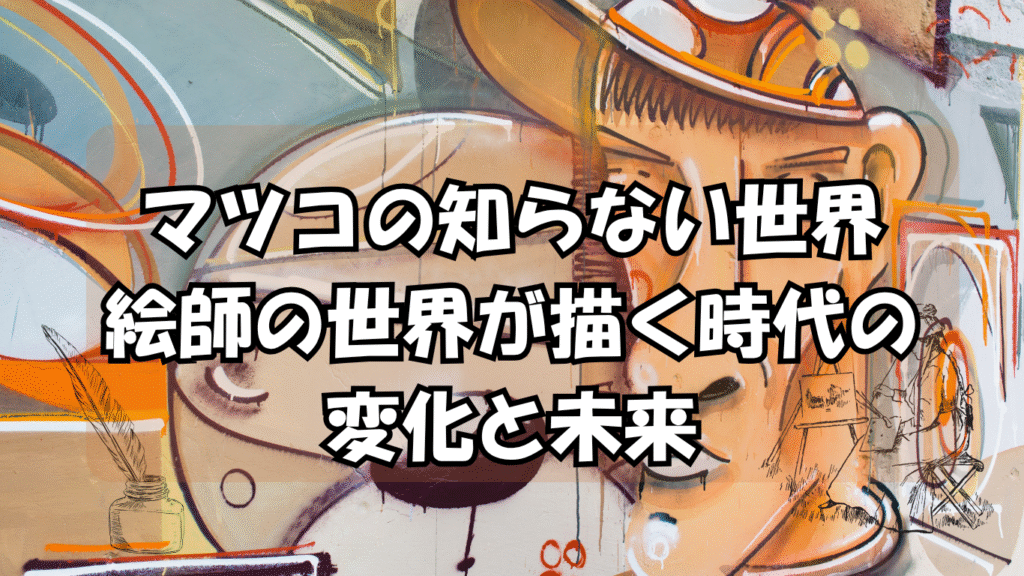
なりたい職業NO1「絵師」時代の到来
2025年、子どもたちの「なりたい職業ランキング」で、ついに“絵師”が1位を獲得しました。
『マツコの知らない世界』でもこの話題が取り上げられ、マツコさんが驚いた表情でこう言いました。
「昔は“漫画家”や“アニメーター”が夢の代表だったのに、今は“絵師”って言葉が子どもたちに浸透してるのね。」
確かに今の時代、絵師という言葉は、ひとつの職業を超えて“新しい生き方”の象徴になっています。
SNSの発展とクリエイター文化の拡散により、「好きな絵を描いて生活する」ことが現実になったのです。
藍にいなさんも番組でこう語っています。
「昔は“絵を描く=趣味”というイメージだったけど、今は描くことで仕事が生まれる。
“誰でも絵師になれる”っていうのは、今の時代を象徴していると思います。」
この変化の背景には、3つの社会的な要因があります。
- SNSとプラットフォームの成熟
X(旧Twitter)、Pixiv、YouTube、Instagram、TikTokなど、絵を発表する場所が無限に広がりました。
「個人が出版社を通さずに作品を届けられる」時代になったことで、才能の発掘が飛躍的に加速。
AIアートツールの発展も、表現の幅を広げています。 - 企業のコンテンツ需要の爆発
VTuber、ボカロ、ゲーム配信、MVなど――企業も個人絵師の“世界観”を求めています。
特にSNSで人気の絵師は、タイアップやコラボでブランドの価値を左右する存在に。
藍にいなさんも、「MVの絵師が誰か」で作品が注目される時代だと語っていました。 - “個人ブランド”としての絵師
絵師は今、会社に属さなくても生きていける職業になっています。
自分の作風がブランド化し、ファンが直接支援する仕組み(BOOTHやPixivFANBOXなど)が浸透したことで、
“好き”と“収入”が直結する新しい働き方が広がりました。
マツコさんは番組中で、「絵師って、アーティストでもあり、経営者でもあるのね」とコメント。
確かに、現代の絵師は「創作」と「発信」を同時にこなすマルチクリエイター。
作品を描くだけでなく、投稿時間やタグ選び、反応分析など、戦略的に行動しているのです。
藍にいなさんは、「発信は絵の延長線上」と表現しました。
「SNSでの投稿も、絵を見せるための“構図”の一部なんです。
見てもらう工夫をすることは、描くことと同じくらい大切。」
番組後、SNSではこんな声が相次ぎました。
「藍にいなさんの話を聞いて、絵師になりたい夢が本気に変わった」
「“誰でも絵師になれる”って言葉に救われた」
「絵師」という言葉には、“自由”と“責任”の両方が含まれています。
自分の感性を信じて描く自由。
そして、作品を通して誰かの感情を動かす責任。
藍にいなさんが番組の最後に語った一言が、すべてを象徴していました。
「絵師って、絵を描く人じゃなくて、“心を動かす人”だと思ってます。」
それは、まさに現代の子どもたちがこの職業に憧れる理由そのもの。
“好き”を“仕事”にできる時代の到来――
絵師という職業は、いま、最もリアルで、最も夢のある生き方なのです。
SNSとデジタル普及で変わるプロ絵師の定義
かつて「プロの絵描き」といえば、出版社やアニメ制作会社などに所属し、依頼を受けて作品を作る人を指していました。
しかし、2025年の今、その定義は大きく変わっています。
『マツコの知らない世界』で藍にいなさんが語ったのは、まさに“現代のプロ絵師像”そのものでした。
「今は、“プロになる”より“プロとして生きる”ことのほうが大切なんです。」
この言葉に、マツコさんも「つまり、肩書きより“続ける力”なのね」と納得の表情。
藍にいなさんは、プロ絵師を“依頼を受けて描く人”ではなく、
「自分の絵を軸に、持続的に活動できている人」と定義しました。
それは、SNS時代における新しい“職業観”でもあります。
プロかどうかを決めるのは、誰かではなくファンとクライアントの信頼。
そして、それを形にしているのがSNSです。
今、絵師がSNSで行っているのは単なる「投稿」ではありません。
それは“ギャラリー運営”であり、“発信型ポートフォリオ”なのです。
このように、絵師たちはSNSを通じて、自分自身のブランドを築いています。
藍にいなさんは、自分の活動を「絵の発信ラボ」と呼んでいます。
「フォロワー数は“数字”じゃなくて“対話の数”。
誰かが見てくれる限り、作品を出す意味がある。」
マツコさんはその言葉に、「それ、ほとんど会社経営じゃないの」と笑いましたが、
実際、現代の絵師はアーティストであり経営者でもあるのです。
SNSを使いこなす力は、単なる宣伝ではなく「信頼の可視化」。
投稿頻度や反応、ファンとの関わりが、企業からの依頼やコラボのチャンスにつながります。
また、デジタル技術の進化も、プロ絵師の定義を変える大きな要因となっています。
ペンタブや液晶タブレット、AIアシストツールの発達によって、制作効率はかつてないほど向上。
個人でも商業レベルの映像やアニメーションを制作できるようになりました。
藍にいなさんは、デジタルツールを“共作する仲間”と呼びます。
「技術を使いこなすことは、手を増やすこと。
でも、“心”まで任せない。そこだけは、描く人の責任です。」
この「技術と心の共存」が、藍にいなさんの作品を際立たせている理由でしょう。
彼女の絵は、どれもデジタルの滑らかさを持ちながら、人間らしい“揺らぎ”が残っています。
番組では、「プロとアマの境目がなくなった現代で、どう“自分をプロ化”するか」という話題にも触れられました。
藍にいなさんはこう答えています。
「絵でお金をもらうこと自体が“プロ”ではないと思ってます。
“誰かの心を動かして、また見たいと思わせること”。
それができたとき、その人はもうプロです。」
マツコさんは少し間をおいて、
「……それ、歌手にも当てはまるわね。」
と呟きました。
藍にいなさんの考える“プロ”とは、資格でも肩書きでもなく“継続する姿勢”です。
絵を描き、発信し、誰かの心を動かし続けること――。
それが、今の時代における「プロ絵師の定義」なのです。
初音ミク・Vtuberがもたらした絵師文化の拡散
「初音ミクがいなかったら、今の絵師文化はここまで広がっていなかったかもしれません。」
『マツコの知らない世界』で藍にいなさんがそう語った瞬間、スタジオは静まり返りました。
彼女の言葉が示すように、初音ミクとVtuberの登場は、絵師という存在を世の中に“見える形”で押し上げた大きな転機だったのです。
■「創作を共有する」文化を作った初音ミク
初音ミクが登場した2007年、誰もが自宅で“曲を作り、絵を描き、動画を投稿できる”時代が始まりました。
ボカロ楽曲を彩るために、多くの絵師たちがキャラクターイラストやMV用のアートを提供し、
「絵 × 音楽 × 映像」のコラボレーション文化が誕生したのです。
藍にいなさんも、この流れに大きな影響を受けた一人。
「初音ミクの世界では、“描きたい人”と“聴かせたい人”が自然に出会えた。
そこから“創作って一人じゃない”って知ったんです。」
マツコさんは、「つまり“絵が音楽の仲間になった”ってことね」とコメント。
まさにその通りで、初音ミクの存在が「絵師=楽曲の共作者」という新しい立ち位置を生み出しました。
この文化は現在のYOASOBIや米津玄師のMV表現にも直結しており、
音と絵が一体となる“視覚の物語”の礎を築いたのです。
■Vtuber時代がもたらした“絵師の表舞台化”
さらに2018年以降、Vtuber(バーチャルYouTuber)の台頭が、絵師文化を新たなフェーズへ押し上げました。
かつては裏方だった絵師が、Vtuberの“デザイン原作者”として名前を知られるようになったのです。
たとえば、「ホロライブ」や「にじさんじ」などの人気Vtuberたちのキャラクターデザインには、
有名なイラストレーターや絵師が多数関わっています。
彼らの描く一枚の立ち絵が、視聴者数百万のファンを魅了する“人格”となるのです。
藍にいなさんもこの流れを「絵の革命」と表現していました。
「昔は“絵は静止画”だったのに、今は“絵が話す”んです。
自分が描いたキャラクターが、言葉を持ち、動いて、世界と会話する――
こんな時代が来るなんて、誰も想像してなかったと思います。」
マツコさんは「キャラが命を持つって、すごいことよね」と感心しきり。
「絵師の名前がクレジットされること自体が、“作り手の時代”を象徴してるのね」と語りました。
■SNSと絵師文化の共鳴
初音ミクとVtuberが広げた“創作共有文化”は、SNSによって一気に拡散しました。
ファンアートを描けば公式が反応し、二次創作が次々に広がる。
この双方向の交流が、絵師たちの創作意欲を爆発的に高めています。
いまでは、
藍にいなさんは「“ファン”と“絵師”の境界がなくなってきている」と話していました。
「誰もが描く側になれる。
“見る”と“描く”を自由に行き来できるのが、今の絵師文化の魅力なんです。」
初音ミクが開いた“創作の民主化”の扉。
Vtuberが加速させた“キャラクターの命”。
そしてSNSが育てた“共感と発信の輪”。
この三つが交わったとき、絵師という存在はひとつのカルチャーを超え、
「人と人をつなぐ表現者」として進化したのです。
マツコさんの最後の言葉が印象的でした。
「あなたたち絵師って、未来を描いてるのね。人がまだ言葉にできない気持ちを、絵で先に見せてくれる。」
それこそが、初音ミクやVtuberが生んだ、絵師文化の最大の功績なのです。
来場者100万人の絵師イベントから見る市場規模
『マツコの知らない世界』では、藍にいなさんが登場するVTRの中で、
“来場者数およそ100万人”を記録した絵師イベントの現場にも密着しました。
この驚異的な数字に、マツコさんは「コミケ並みじゃないの!?」と驚嘆。
そう、絵師の世界はいま、まさに巨大な経済と文化の中心へと進化しているのです。
■「見る」から「参加する」イベントへ
かつては、絵師イベントといえば“展示会”や“即売会”のように、作品を“鑑賞する場所”が主流でした。
しかし、2020年代後半に入ると、そのスタイルが大きく変化します。
来場者が“描く側”として参加する体験型イベントが急増したのです。
番組で紹介されたイベントでは、
マツコさんは現場の映像を見ながら、
「これ、もはや“フェス”ね。音楽じゃなくて絵で盛り上がるフェス。」
とコメント。
藍にいなさんも「まさにそうなんです。絵師イベントは“創作の祭典”なんです」と笑顔で答えていました。
■市場規模は年々拡大、関連ビジネスも急成長
デジタルイラスト関連の市場は、2025年現在で年間2000億円規模に達するといわれています。
SNSやストリーミングの拡大によって、個人クリエイターが直接収益を得る仕組みが確立された結果、
藍にいなさんは、「絵師は今や“クリエイティブ産業の中核”」と表現しています。
「昔はアニメや漫画の一部だったけど、今は“絵師そのもの”がブランド化している。
名前だけで人を集められる人が増えたのは、この数年の大きな変化ですね。」
■ファンとの距離が近い「直接交流」の魅力
イベントの最大の特徴は、“作り手とファンが直接会える”こと。
藍にいなさんも、初めてファンに直接声をかけられたときの感動を語っていました。
「“あなたの絵で救われました”って言われた瞬間、泣きそうになりました。
SNSのコメントでは感じられない、リアルな“温度”があるんです。」
マツコさんはその言葉に静かに頷き、
「デジタルの世界でやってることが、ちゃんと現実の世界に繋がってるのね」とコメント。
まさに、絵師という存在が“オンラインとオフラインの橋渡し”を担っているのです。
■「絵で経済が動く」時代へ
番組では、経済的な側面にも触れられました。
イベントの来場者が購入するグッズや同人誌、限定アートプリントなどの売上は、1日で数億円規模に上ることも。
また、企業ブースでは最新の液タブやペイントソフトが展示され、絵師向けツール市場も急成長しています。
絵師はもはや「個人クリエイター」ではなく、産業を動かすプレイヤーになっているのです。
藍にいなさんはこう語りました。
「絵師が集まるイベントって、“経済活動”でもあり“文化活動”でもある。
アートとビジネスが共存できる場所が増えたのが、本当に嬉しい。」
■マツコの感想と時代の転換点
マツコさんはイベントのVTRを見終えた後、こんな言葉を残しました。
「昔は“絵を描いて食べていくなんて無理”って言われてたのに、今は“絵で世界を動かす人”がいるのね。
これ、すごいことよ。」
彼女の言葉に、藍にいなさんは優しく微笑みながら答えました。
「好きなことを続けるって、努力より“勇気”のほうが必要なんです。
でも、こうして絵師たちが集まる場所があるから、また明日も描けるんです。」
絵師文化の広がりは、もはや一部のオタクカルチャーではなく、日本の新しい経済・文化の柱へと変貌しています。
100万人が集うイベントは、単なるお祭りではなく、
“好き”を力に変える人たちの証。
それは、藍にいなさんが語った「絵師は社会を動かす存在」という言葉を、見事に裏づけるものでした。
アニメーション制作とイラストの融合トレンド
『マツコの知らない世界』では、藍にいなさんが“絵師”という存在を語る中で、
今の時代を象徴するキーワードとして何度も口にしたのが、「イラストとアニメーションの融合」でした。
近年、静止画と動画の境界がどんどん曖昧になり、
1枚の絵が“動く物語”を語り始めています。
藍にいなさんの代表作「夜に駆ける」も、その典型。
一枚一枚の絵が音楽と呼吸を合わせながら、
“動かずに動いている”という新しい映像表現を確立しました。
■「1枚絵」が物語を持つ時代へ
かつてアニメーションは“何千枚もの絵を動かす”ものでしたが、
今のトレンドは「1枚絵の中で動きを感じさせる表現」へと進化しています。
藍にいなさんはそれを「感情のモーション」と呼びました。
「風に髪が揺れる」「光が差す」「瞳が潤む」――
実際に動いていないのに、見る人の脳内で動きを“感じさせる”。
これはまさに、イラストとアニメーションの融合が生んだ新たな“心理的演出”なのです。
マツコさんは、「絵が止まってるのに“息してる”ように見える」と感嘆。
藍にいなさんは静かに微笑んでこう答えました。
「それが、絵に命を吹き込む瞬間なんです。」
■デジタルツールが広げた“動く絵”の表現
このトレンドを支えているのが、デジタルアニメーション技術の進化です。
After Effects、CLIP STUDIO、Procreate、Blenderなど、
今では個人でも高品質なアニメーションを制作できる環境が整っています。
特に注目されているのが、“イラストから動きを生成する”新しいスタイル。
たとえば1枚絵にパーツ分けを施し、キャラクターの表情や背景を軽く動かす。
これにより、たった一枚のアートでも“映像作品”として成立するようになったのです。
藍にいなさんも番組で、
「最近は“描く”と“動かす”が同時に行われるようになりました。
筆の動き自体が、もうアニメーションなんです。」
と語っていました。
■SNS発のショートアニメ文化の拡大
TikTokやYouTube Shortsの流行も、イラスト×アニメの融合を加速させています。
15〜60秒ほどの短い映像に、音楽とストーリーを込める“ショートアニメ”が急増。
絵師が自ら脚本・作画・編集を行う「個人制作アニメ」が、
SNSで数百万再生を超える時代になりました。
番組では、藍にいなさんがリスペクトしている若手クリエイターの例も紹介。
「1枚の絵で世界観を作り、その中に小さな動きを入れる。
“全部を見せない”ことで、想像の余白が生まれるんです。」
この“見せすぎない表現”こそが、今の時代のトレンド。
視聴者が「続きを想像したくなる」余白こそが、アートの余韻を生むのです。
■アニメとイラストの垣根を壊す「表現者」の誕生
マツコさんは「あなたの話を聞いてると、もう“絵師”って職業名じゃ追いつかないわね」と笑いながら言いました。
確かに、藍にいなさんをはじめとする現代の絵師は、アニメーターでもあり、映像監督でもあり、詩人でもある。
彼らはジャンルの垣根を軽やかに越えながら、“感情を絵で映像化する”表現者へと進化しています。
藍にいなさんは、「ジャンルを決めるのは見る人でいい。
自分は“描きたい気持ち”が動く方向に進むだけ」と語りました。
この姿勢に、マツコさんは深く頷き、
「あなたみたいな人が増えたら、日本のアニメの未来は明るいわね」とコメント。
■「静」と「動」の融合がもたらす未来
絵が動く。音が見える。物語が一瞬で伝わる。
この融合が進むことで、表現の自由度は無限に広がります。
そして藍にいなさんは、最後にこんな言葉を残しました。
「絵って、止まってるものじゃなくて、“生きてる瞬間”を閉じ込めたものなんです。
それが動き出したら、もう命ですよ。」
その言葉に、マツコさんは思わず「名言出たわね」と微笑みながら拍手。
いま、アニメーションとイラストは競い合うのではなく、手を取り合っています。
“動かす絵師”と“描くアニメーター”の境界が消え、
そこに新しい表現の地平が生まれている――。
それが、2025年の絵師業界が描く“未来のアートシーン”なのです。
次世代クリエイターに必要なスキルと発信力
『マツコの知らない世界』の終盤で、藍にいなさんが特に熱を込めて語ったのが、
“これからの時代に活躍できるクリエイターに必要なスキルと発信力”でした。
「絵が上手いだけでは届かない。
でも、“誰かの心に届く”絵なら、必ずどこかで見つけてもらえる。」
この言葉は、多くの若い視聴者の胸に深く刺さりました。
■テクニックよりも「観察力」と「感情力」
藍にいなさんは、技術よりもまず大切なのは“観察する力”だと語ります。
「どんなに綺麗な絵でも、“何を感じて描いているか”が伝わらないと、人の心は動かないんです。」
彼女は、日常の中からインスピレーションを得ることを大切にしているそうです。
こうした“感情のきらめき”を絵に落とし込むことで、
見る人が「自分の気持ちだ」と共鳴してくれる。
マツコさんも「技術より“心のピント”を合わせるのね」と感心していました。
■多様なツールを使いこなす柔軟性
次世代クリエイターには、複数のツールを自由に扱う力も求められています。
藍にいなさん自身、PhotoshopやCLIP STUDIO、After Effects、Blenderなどを組み合わせながら制作しています。
「ツールを変えると“思考”も変わるんです。
アナログで描くときは感覚的に、デジタルでは構造的に。
そのバランスを取るのが、今の時代の絵師の面白さですね。」
つまり、技術の幅は表現の幅。
“描けること”よりも、“どう描くか”を選べる自由こそが、次世代の強みなのです。
■SNS発信は「作品の一部」
藍にいなさんが特に強調したのは、「発信も創作の一部」という考え方。
「投稿のタイミング、文章の言葉、ハッシュタグ――全部が“作品を届ける演出”なんです。」
たとえば、彼女はYOASOBI「夜に駆ける」のMVを投稿する際、
リリースの3日前から“空を駆ける少女のシルエット”を少しずつ公開していました。
その断片的な投稿がファンの期待を高め、公開と同時に爆発的な拡散を生んだのです。
マツコさんは「SNSってただの宣伝ツールじゃなくて、“物語の舞台”なのね」と驚きました。
藍にいなさんは微笑みながら、
「投稿って、言葉のない“会話”なんです。
“見てくれてありがとう”を絵で伝えるような感覚です。」
■“数字”より“響き合い”を大切にする
現代のSNSでは、フォロワー数や「いいね」の数が評価基準になりがちです。
しかし藍にいなさんは、そこに縛られない姿勢を貫いています。
「“バズる”より、“残る”絵を描きたい。
数字は一瞬だけど、心に残る絵は一生です。」
彼女のアカウントには、「あなたの絵で勇気が出た」「この色に救われた」というコメントが多数寄せられています。
この“共鳴の連鎖”こそが、彼女の最大の発信力。
■コラボレーションと自己表現の両立
次世代の絵師に求められるのは、“他者と作る力”と“自分を貫く力”の両立です。
藍にいなさんは、音楽家・映像監督・アニメーターなど、さまざまな分野のクリエイターとコラボしています。
その中で大切にしているのは、「相手の世界観を理解しながら、自分の線を失わないこと」。
「コラボって、“混ざる”ことじゃなくて“響き合う”ことなんです。」
この言葉にマツコさんは、「あなた、哲学者ね」と笑いながらも納得の表情。
■“好き”を継続できる仕組みを作る
最後に藍にいなさんが伝えたのは、クリエイターとして生きるために欠かせない“持続力”の話でした。
「絵を描き続けるには、体力もお金も必要です。
だからこそ、自分のペースで働ける環境を作ることが大事なんです。」
彼女は現在、
「1本の柱に頼らず、3本くらいの“好き”を育てておくと、創作が続けやすいですよ。」
その現実的なアドバイスに、マツコさんも「ほんとに経営者ね」と笑っていました。
いま、絵師は“描く力”だけでは成功できません。
観察力、共感力、デジタルリテラシー、発信力――それらすべてが“表現の翼”になります。
藍にいなさんが番組の最後で語った言葉が、すべてを象徴していました。
「絵って、結局“生き方”なんです。
だからこそ、自分を好きでいられる描き方を選んでほしい。」
その言葉に、マツコさんが深く頷きながら「あなた、もう完全に“時代の先生”よ」と微笑んだシーンが印象的でした。
マツコの知らない世界 絵師の世界と藍にいなが示す創作の未来を総括
2025年10月7日放送の『マツコの知らない世界』――
“絵師の世界”をテーマに、藍にいなさんが語った数々の言葉は、
いまを生きるすべてのクリエイターに向けた“未来の宣言”のようでした。
マツコさんが何度も口にしていたのは、「絵師って、もうアーティスト以上の存在ね」という言葉。
藍にいなさんの描くビジョンは、単なる「絵を描く仕事」の枠を超えて、
“人の感情を動かし、時代を映す表現者”としての新しい生き方を提示していたのです。
■番組で語られた絵師の本質と未来のヒント(要約)
■今の時代を象徴する“絵師”という生き方
この放送が示したのは、単なる職業紹介ではありません。
むしろ、「絵師」という存在が、令和時代の“夢の形”を体現しているということ。
かつて「絵で食べていくのは難しい」と言われた時代から、
今では「絵で人を動かす」「絵で社会を変える」時代へ。
藍にいなさんのように、SNSを通じて自分の世界を発信し、
企業やアーティストと対等にコラボしながら、自分の表現を貫く人が増えています。
マツコさんも、「あなたたちがやってることって、アートとビジネスの融合よね」と言い、
まさに“クリエイティブ・エコノミー”の最前線がここにあることを示しました。
■藍にいなが語った「これからの創作」
番組の最後、藍にいなさんは静かに、しかし力強く語りました。
「これからの時代、絵を描くことは“自己表現”じゃなくて“他者との対話”になると思います。
誰かの記憶や痛みを受け止めて、それを絵で返す。
そんな優しい循環がもっと広がったらいいなと思います。」
マツコさんは涙ぐみながら、「言葉より絵のほうが伝わることって、確かにあるのよね」と呟きました。
■次世代に残したメッセージ
藍にいなさんが若い絵師たちに伝えたメッセージは、とてもシンプルで、しかし本質的でした。
このメッセージは、すべてのクリエイターに向けた応援歌のように響きました。
■マツコが語った「絵師という時代」
番組の締めくくりで、マツコさんは深く息を吸い、こう語りました。
「あなたたち絵師が見せてくれる世界って、
みんなが心の中に持ってる“言葉にならない気持ち”なのよね。
だからこそ、絵師って、時代の“代弁者”なのかもしれない。」
そして最後に――
「この世界、知らなきゃもったいないわよ。」
と微笑んで番組を締めくくりました。
■この記事の総括ポイント(15項目)
絵師はもう、キャンバスの中に閉じ込められた存在ではありません。
SNSの中で、映像の中で、人の心の中で――彼らは生きています。
そして、その筆の一振りが、誰かの人生を変えるかもしれない。
藍にいなさんが見せた“絵師の世界”は、まさに未来のアートそのものでした。
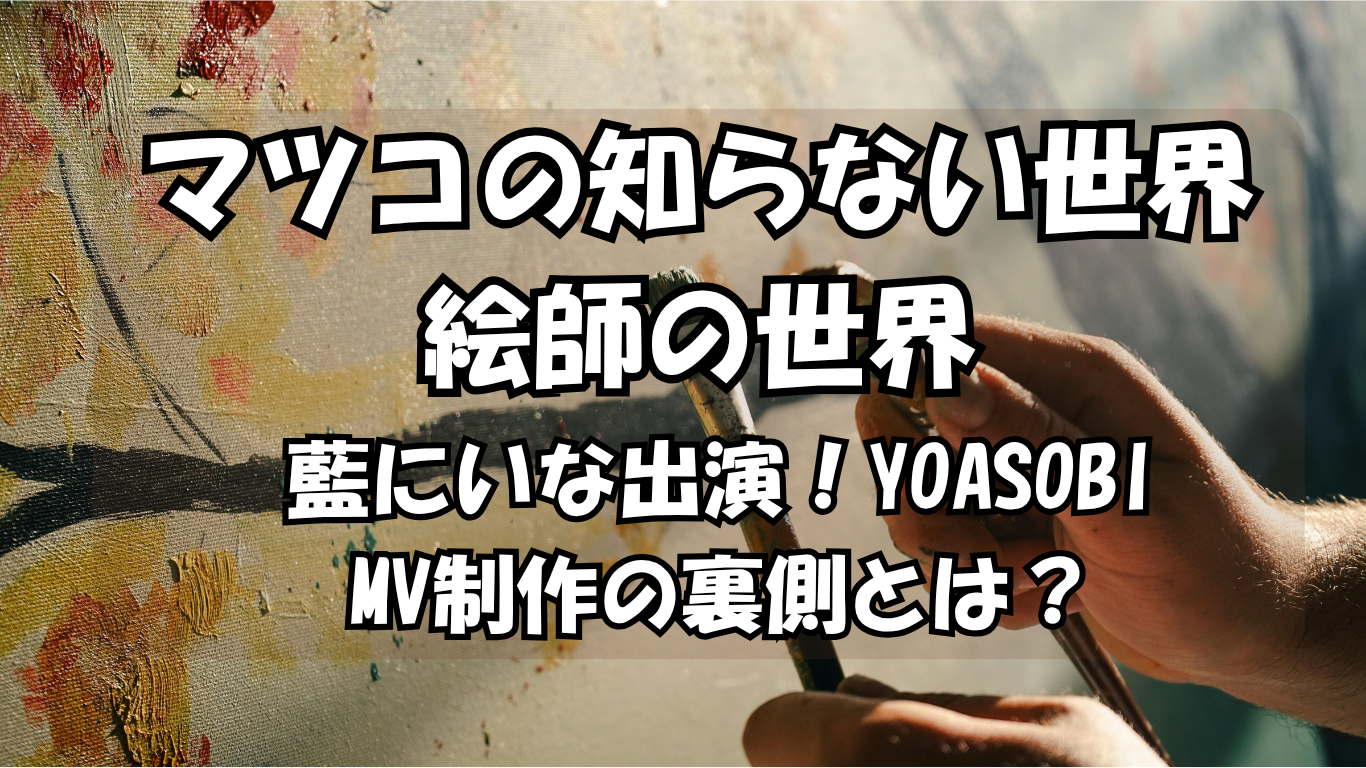
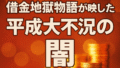
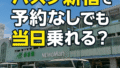
コメント