本記事は、PRも含みます。
夜の街に灯る小さな明かり。
その一つひとつが、人のぬくもりと物語を映し出す「屋台村」。
「行ってみたいけど、少し勇気がいる…」
「どんな人が屋台村を巡っているの?」
そんな疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。
2025年11月11日放送の「マツコの知らない世界」では、
全国1000軒以上の屋台村を巡った“屋台村スペシャリスト”ヒデさんが登場します。
彼が見てきたのは、ただの飲み屋の集まりではなく、
「人と人が心でつながる日本の原風景」でした。
この記事では、そんなヒデさんの人生と活動、
そして彼が紹介する全国の屋台村の魅力を、わかりやすく丁寧にお伝えします。
この記事で分かること
ヒデさんが1000軒を巡って見つけた“人のあたたかさ”と“食の物語”。
あなたもこの記事を読み終える頃には、
きっと「屋台村へ行ってみたい」と思いますよ!
マツコの知らない世界 屋台村の世界 ヒデさんとは?徹底プロフィールと経歴
「マツコの知らない世界 屋台村の世界」に出演したヒデさんは、全国の屋台村を1000回以上巡った日本屈指の屋台村スペシャリストです。
彼の活動はテレビだけでなく、ブログやSNS、地域イベントなど多岐にわたっています。
屋台村というと、福岡のような移動式の屋台を思い浮かべる人も多いですが、
ヒデさんが主に訪れているのは、私有地に常設された“固定型屋台村”。
つまり、その街に根ざし、地域の人たちとともに育っていくタイプの屋台村です。
彼の旅の目的は「食べ歩き」ではありません。
それは「屋台村という“人と文化の交差点”を記録すること」。
一軒一軒で出会う人の温かさや、そこに流れる時間、
地域ごとに異なる“屋台文化”の違いを見つめ続けてきたのです。
ヒデさんの活動の中心は、自身が運営するサイト「屋台村ラリー」。
全国各地の屋台村を実際に訪れ、その体験を写真と文章で紹介することで、
屋台村を知らない人たちにもその魅力を発信しています。
また、ヒデさんは単なるブロガーではなく、“現場に足を運ぶ研究者”のような存在。
一軒の屋台に何度も通い、店主や常連との関係を築きながら、
その地域の“人情の風景”を掘り下げて記録しています。
マツコ・デラックスさんとの共演では、
「ヒデさんの人生そのものが、屋台村そのものみたい」と評されたほど。
笑顔の奥にある真剣な探究心と、現場で得たリアルな経験談が、
番組内でも多くの共感を呼びました。
彼の言葉を借りるなら、
「屋台村は、料理を食べる場所じゃなくて、人のぬくもりを味わう場所。」
まさにその一言が、ヒデさんという人物のすべてを表しています。
ヒデさんの本名・出身地・職業は?
「ヒデさん」という名前で活動している彼の本名は非公開ですが、
ファンの間では「旅するヒデさん」や「屋台村のヒデさん」として親しまれています。
出身は北海道。
その地で初めて訪れた屋台村「北の屋台」(帯広)が、彼の人生を大きく変えるきっかけとなりました。
地元の人たちの温かさ、カウンター越しに交わされる会話、
その“人と人がつながる空気”に魅了され、
全国の屋台村を巡る旅が始まったのです。
職業は、もともと一般企業に勤める社会人でした。
しかし、旅を重ねるうちに「屋台村を記録し、文化として残したい」と感じ、
現在は「屋台村ラリー」の管理人兼ライターとして活動しています。
取材・撮影・執筆・SNS発信をすべて一人で行うその姿勢は、まさに情熱そのもの。
ヒデさんは、自身の活動を「仕事」ではなく「使命」と語っています。
「屋台村は、地域の人の努力と情熱で成り立つ“生きた文化”です。
それを次の世代にも伝えていきたい。」
この想いが、多くの人の共感を呼び、テレビ出演にもつながりました。
実際、放送前からSNSでは「ヒデさんついに地上波!」と話題になり、
番組放送後には屋台村に足を運ぶ人が急増しています。
ヒデさんの魅力は、どんな屋台村でもすぐに溶け込み、
まるで地元の一員のように常連や店主と打ち解ける“人間力”。
その自然体な姿勢が、屋台村という場所の本質を伝える大きな力になっているのです。
1000軒以上巡った屋台村の記録と軌跡
ヒデさんがこれまでに訪れた屋台村の数は、なんと1000軒以上。
これは日本全国に存在する屋台村のほとんどを網羅する驚異的な記録です。
彼は単に数を競うわけではなく、
「その土地の空気と人を感じる」ことを大切にしています。
訪れた屋台村の多くには、一期一会の物語があります。
地元で長年店を構える店主との出会い、
観光客との偶然の乾杯、
地元祭りと一緒に盛り上がる夜。
「屋台村は、同じように見えて一つとして同じ場所はない。」
とヒデさんは言います。
旅の記録はすべてノートとカメラに残され、
その数はすでに膨大な量に達しています。
屋台ごとにメモされた“おすすめ料理”や“人とのエピソード”には、
一つひとつに温かみがあり、読むだけで旅をしている気分になるほどです。
たとえば、帯広の「北の屋台」では、
雪の降る夜に地元客と一緒に鍋を囲みながら語り合った思い出。
八戸の「みろく横丁」では、偶然隣に座った出張中のサラリーマンと友達になり、
その後も交流が続いているという話も。
こうした経験を通じてヒデさんが得たのは、
“屋台村は人と人をつなぐ小さな社会”という確信です。
そして、その体験が「屋台村ラリー」の原動力となっています。
全国を巡る中で、
・営業スタイルの違い(移動式と固定型)
・地域による料理の個性
・客層や人間関係の特徴
などをデータとして整理し、
「屋台村文化の地域比較レポート」も制作中とのこと。
このように、ヒデさんの旅は単なる“食べ歩き”ではなく、
日本の地域文化を記録する活動そのもの。
屋台村を1000軒巡るという数字の裏には、
無数の人との出会いと感動が刻まれているのです。
ヒデさんが注目する「固定型屋台村」とは
ヒデさんが特に注目しているのが、「固定型屋台村」と呼ばれるスタイルです。
一般的に「屋台」と聞くと、福岡のように移動式の屋台を思い浮かべる人が多いでしょう。
しかしヒデさんが愛するのは、私有地などに常設された小さな飲食店の集合体である固定型屋台村です。
固定型屋台村は、移動しない代わりに地域密着型のコミュニティ空間として発展してきました。
それぞれの店舗がカウンターだけの小さな空間で営業しており、
客同士や店主との距離が近く、自然と会話が生まれるのが特徴です。
ヒデさんはこう語ります。
「固定型屋台村は“街の名刺”のような存在。
その街の文化、人柄、食の特徴がすべて詰まっている。」
固定型屋台村の魅力を語る上で欠かせないのが、地域再生の役割です。
実際、帯広の「北の屋台」や八戸の「みろく横丁」などは、
一度は衰退しかけた商店街を再び活気づけた象徴的存在です。
固定型屋台村のメリットは次の通りです。
一方で、課題もあります。
ヒデさんは、こうした現実も包み隠さず発信しています。
「屋台村は楽しいだけの場所じゃない。支える人がいてこそ続く文化です」と語り、
現地で働く人たちへの敬意を常に忘れません。
彼にとって固定型屋台村は、“地域の心が形になった場所”。
料理だけでなく、空間そのものがその土地の物語を語っているのです。
屋台村を巡るきっかけとマツコとの出会い
ヒデさんが全国の屋台村を巡り始めたのは、偶然の出会いがきっかけでした。
もともと旅行とお酒が好きだったヒデさん。
ある冬の夜、北海道・帯広を訪れた際、偶然入ったのが「北の屋台」でした。
そこで出会った店主や常連たちの温かいもてなしに心を打たれ、
「こんな人情が生きている場所がまだ日本にあるのか」と感動。
その日を境に、屋台村巡りの旅が始まりました。
最初は仕事の合間に訪ねる趣味の延長でしたが、
気づけば各地の屋台村を写真に収め、記録し、
ブログ「屋台村ラリー」として公開するようになります。
やがてその情熱がSNSで話題となり、
多くのフォロワーが「次はどこの屋台村に行くの?」と注目する存在に。
その活動がテレビ業界の目に留まり、
ついにTBSの人気番組『マツコの知らない世界』の制作チームから声がかかりました。
番組スタッフがヒデさんに興味を持った理由は、
“屋台村を単なる飲食の場ではなく、人と街をつなぐ文化として見ている”こと。
他の食通とは一線を画すその視点に、マツコ・デラックスさん自身も大いに共感したといいます。
収録当日、マツコさんは開口一番にこう言いました。
「あんたの生き方そのものが屋台村なのよ。」
その言葉にヒデさんは思わず笑顔に。
「マツコさん、うまいこと言いますねぇ」と照れながら答えたそうです。
番組では、北は北海道から南は沖縄まで、ヒデさんが巡った屋台村の写真やエピソードが紹介されました。
特に帯広の「北の屋台」と鹿児島の「かごっま屋台村」の話では、
マツコさんが「行きたい!」と本気で興味を示すほど。
この放送をきっかけに、屋台村の魅力が全国的に知られるようになり、
観光客が増加した地域も少なくありません。
ヒデさんにとってマツコさんとの出会いは、
「屋台村を全国に伝えるきっかけをくれた恩人」と語るほど大きな出来事でした。
次の見出しに進んでもよろしいですか?
InstagramやSNSで見られる活動の様子
ヒデさんは、テレビだけでなく、SNSでも積極的に情報発信を行っています。
とくにInstagramでは、彼の日常の屋台村巡りがリアルタイムで共有されています。
投稿内容は、ただの「食レポ」ではありません。
屋台の灯り、湯気、笑顔、そしてその夜の空気までが伝わる写真と、
温かくユーモラスなキャプションが添えられています。
たとえば、帯広の「北の屋台」で撮影した写真には、
「今日は地元の方に教えてもらった味噌ホルモン。
外は氷点下でも、屋台の中は心まであったかい。」
というコメントが。
見るだけで、まるでその場にいるような臨場感があります。
また、屋台村の最新情報も発信中。
新しい屋台のオープン情報や、閉店した店への感謝メッセージなど、
“現場を歩く人の声”として信頼を集めています。
フォロワーの声も多数。
「ヒデさんの投稿見て、初めて屋台村に行ってみた!」
「旅の目的が“屋台村”になったのはヒデさんのおかげ」
といったコメントが並び、ファンの中には彼を“屋台村の伝道師”と呼ぶ人もいます。
Instagramのストーリーズでは、各地の店主とのツーショットや、
屋台の裏側のシーンなども見ることができ、まるで“旅のアルバム”のよう。
ヒデさん自身もSNSを「屋台村文化のアーカイブ」と位置づけています。
「いつか屋台村が減ってしまっても、
写真や言葉で残せば、誰かの心にまた灯りがともる。」
その思いが、画面越しにも伝わる温かさを生んでいます。
マツコの知らない世界 屋台村の世界 ヒデさんが語る日本全国屋台村の魅力
ヒデさんが全国を巡る中で見つけたのは、「屋台村」という文化が地域ごとにまったく違う顔を持っているということでした。
北海道の雪の中で湯気が立ち上る温かな屋台村。
東北の人情あふれる酒場通り。
九州の活気に満ちた夜の笑い声。
そして、南国・沖縄の風を感じるリゾート屋台村。
どの屋台村にも共通しているのは、人と人をつなぐ不思議な力です。
ヒデさんはこう語ります。
「屋台村は“その街の縮図”。
料理よりも、人の笑顔が主役なんです。」
彼の旅はまるで、日本中の“夜の人間模様”を記録する文化探索のよう。
この章では、ヒデさんが実際に訪れた屋台村の中から、特に印象深い4つのエリアを紹介します。
帯広「北の屋台」から始まる北海道の屋台文化
ヒデさんの屋台村巡りの原点ともいえるのが、北海道・帯広の「北の屋台」です。
2001年に開業したこの屋台村は、日本における「現代型屋台村ブーム」の火付け役。
全20店舗が並び、わずか1.8メートル幅の小さな屋台がぎゅっと立ち並ぶ様子は、まるで昭和の路地裏にタイムスリップしたような懐かしさを感じさせます。
「北の屋台」は、ただの飲み屋街ではなく、地域再生プロジェクトとして誕生しました。
かつて帯広の中心市街地が空洞化し、商店街が寂れていく中で、
地元の経営者たちが「街に人の笑顔を取り戻したい」と立ち上げたのが始まりです。
各屋台は若手起業家に貸し出され、一定期間ごとに入れ替わる仕組み。
この“チャレンジ制度”によって、常に新しい料理や個性が生まれ、街に活気を与え続けています。
ヒデさんは初めて訪れたときの感動を、こう振り返ります。
「カウンター越しに“どこから来たの?”って声をかけられて、
気づいたら隣の人と乾杯してました。あれが屋台村の魔法ですね。」
実際、「北の屋台」は観光客だけでなく、地元の常連にも愛されています。
週に何度も通う人も多く、「今夜もいつもの顔に会える」と安心して訪れる場所になっています。
さらに驚くのは、冬でも営業していること。
屋台の中はストーブが完備され、雪の中でも温かい笑顔が絶えません。
まさに「北の大地に灯る人情の灯り」と呼ぶにふさわしい場所です。
最近では海外からの観光客も増えており、英語メニューを置く店も登場。
“世界で一番温かい寒さの中の屋台村”として、国際的にも注目されています。
ヒデさんにとって「北の屋台」は、すべての屋台村の出発点。
「ここで感じた人のぬくもりが、全国を巡る原動力になった」と語っています。
八戸「みろく横丁」と東北の人情屋台の魅力
青森県八戸市にある「みろく横丁」は、東北の屋台村文化を代表する存在です。
2002年にオープンしたこの屋台村は、現在26店舗が軒を連ねる温かな通りで、
八戸の人情と食文化を凝縮した“小さな街”のような場所です。
名前の「みろく」とは、八戸の中心商店街「三日町」と「六日町」の間に位置することから名付けられました。
狭い通路に立ち並ぶ屋台には、海鮮料理、郷土の煮込み、地酒など、東北の魅力がぎゅっと詰まっています。
ヒデさんはこの場所を「心がほどける屋台村」と表現します。
「北国の人はシャイだと思われがちですが、ここでは誰もが笑顔になる。
隣に座った知らない人とも、気づけば話して、乾杯してるんです」と語っています。
実際に訪れた人たちからもこんな声が寄せられています。
この「みろく横丁」には、ユニークな取り組みもあります。
これらの活動により、みろく横丁は単なる飲み屋街を超え、地域再生のシンボルとなっています。
また、2024年4月にはリニューアルが行われ、26店中13店が新規出店。
新旧が共存する形で、伝統と革新のバランスを保ちながら進化を続けています。
ヒデさんもこのリニューアル直後に訪れ、SNSでこうコメントしています。
「変わっても変わらない“温かさ”がここにある。
八戸の夜は今日も人の笑顔で満ちている。」
みろく横丁はまさに、東北の人情と復興の象徴。
訪れた誰もが「また帰りたい」と思う、不思議な力を持つ屋台村です。
鹿児島「かごっま屋台村」と九州の活気
〒890-0053 鹿児島市中央町11番地
南九州・鹿児島の中心地にある「かごっま屋台村」は、九州の底抜けの明るさと食文化を象徴する場所です。
2012年に開業し、黒豚料理、地鶏、さつま揚げ、そして本場の芋焼酎がずらりと並ぶ、まさに“九州のうまかもん横丁”。
ヒデさんが初めて訪れたとき、最初に感じたのは「熱気」でした。
屋台から流れる笑い声、焼酎を片手に語り合う人々、店主の威勢のいい声。
どの瞬間も“鹿児島の夜”そのもので、まるで祭りのような雰囲気に包まれています。
「北の屋台が“静かな温かさ”なら、かごっま屋台村は“陽気な情熱”です」
とヒデさんは語ります。
特に印象的なのは、鹿児島の人たちの“焼酎愛”。
屋台村内の多くの店では、30種類以上の芋焼酎を常備しており、
「今日は“魔王”で」「やっぱ“島美人”やろ」といった会話が自然に飛び交います。
初めて会った人同士が一杯の焼酎で意気投合する光景も珍しくありません。
また、かごっま屋台村では地元農産物を活かした創作料理も人気です。
黒豚しゃぶしゃぶやキビナゴの刺身、地鶏の炭火焼など、どの料理も地元の誇りを感じさせます。
ヒデさんはSNSでこう投稿しています。
「“お帰りなさい”って言われたのは初めて。
一度来た客を“仲間”として迎える。これが鹿児島の屋台村文化だと思う。」
この言葉の通り、かごっま屋台村では“リピーター文化”が根づいています。
常連も観光客も分け隔てなく笑い合い、自然と交流が生まれる。
まさに「屋台村=人の輪」の典型例です。
さらに注目すべきは、地元若者の起業支援にもつながっている点。
屋台を卒業して自分の店を構える人も多く、地域経済の育成モデルとして全国から注目を集めています。
九州らしい情熱と優しさが共存する「かごっま屋台村」。
ヒデさんは「ここに来ると元気を分けてもらえる」と語り、何度も足を運んでいるそうです。
沖縄「国際通り屋台村」南国スタイルの楽しみ方
沖縄といえば、美しい海、ゆったりとした時間、そして人懐っこい笑顔。
そんな“南国の空気”をそのまま体感できるのが、那覇市の中心・国際通り屋台村です。
2015年にオープンしたこの屋台村は、観光名所「国際通り」の一角にあり、
地元の食材と沖縄文化をテーマにした20軒以上の屋台が軒を連ねています。
ヒデさんが初めて訪れたとき、感じたのは“風の屋台村”という独特の開放感でした。
外の風が吹き抜けるオープンスタイルの屋台では、
島唄が流れ、オリオンビールを片手に観光客と地元の人が笑い合っています。
「ここは“屋台村”というより“お祭り会場”のよう。
誰もがリゾート気分で自然に仲良くなれるんです。」
とヒデさんは語ります。
料理の特徴も個性的で、
沖縄そば、ラフテー、タコライス、海ぶどうなど、沖縄ならではのグルメが勢ぞろい。
夜になると、泡盛を片手に「カリー!(乾杯!)」の声があちこちで響きます。
また、国際通り屋台村では、観光客向けに島民との交流イベントも実施されています。
三線ライブ、エイサー演舞、島唄体験など、
「食べて・聞いて・踊って楽しむ屋台村」としても人気です。
ヒデさんはこの屋台村について、SNSでこう綴っています。
「屋台なのに南国の風が吹いてくる。
この自由さこそ、沖縄らしい“人と人との距離の近さ”だと思う。」
さらに、店主たちの明るさも魅力のひとつ。
「いちゃりばちょーでー(出会えば皆兄弟)」という沖縄の言葉どおり、
初対面でも笑顔で迎えてくれる温かさに、誰もが心をつかまれます。
国際通り屋台村は、まさに“沖縄の縮図”。
ヒデさんにとっても「旅の終わりに立ち寄ると、また旅に出たくなる」不思議な場所だそうです。
沖縄「国際通り屋台村」南国スタイルの楽しみ方
沖縄といえば、美しい海、ゆったりとした時間、そして人懐っこい笑顔。
そんな“南国の空気”をそのまま体感できるのが、那覇市の中心・国際通り屋台村です。
2015年にオープンしたこの屋台村は、観光名所「国際通り」の一角にあり、
地元の食材と沖縄文化をテーマにした20軒以上の屋台が軒を連ねています。
ヒデさんが初めて訪れたとき、感じたのは“風の屋台村”という独特の開放感でした。
外の風が吹き抜けるオープンスタイルの屋台では、
島唄が流れ、オリオンビールを片手に観光客と地元の人が笑い合っています。
「ここは“屋台村”というより“お祭り会場”のよう。
誰もがリゾート気分で自然に仲良くなれるんです。」
とヒデさんは語ります。
料理の特徴も個性的で、
沖縄そば、ラフテー、タコライス、海ぶどうなど、沖縄ならではのグルメが勢ぞろい。
夜になると、泡盛を片手に「カリー!(乾杯!)」の声があちこちで響きます。
また、国際通り屋台村では、観光客向けに島民との交流イベントも実施されています。
三線ライブ、エイサー演舞、島唄体験など、
「食べて・聞いて・踊って楽しむ屋台村」としても人気です。
ヒデさんはこの屋台村について、SNSでこう綴っています。
「屋台なのに南国の風が吹いてくる。
この自由さこそ、沖縄らしい“人と人との距離の近さ”だと思う。」
さらに、店主たちの明るさも魅力のひとつ。
「いちゃりばちょーでー(出会えば皆兄弟)」という沖縄の言葉どおり、
初対面でも笑顔で迎えてくれる温かさに、誰もが心をつかまれます。
国際通り屋台村は、まさに“沖縄の縮図”。
ヒデさんにとっても「旅の終わりに立ち寄ると、また旅に出たくなる」不思議な場所だそうです。
常連との交流を楽しむ「屋台村の極意」
屋台村の最大の魅力——それは、“人との距離の近さ”にあります。
けれど、常連さんばかりの雰囲気に「話しかけていいのかな?」と戸惑う人も多いでしょう。
そんなときこそ、ヒデさんが提唱する“屋台村の極意”が役立ちます。
彼はこう言います。
「屋台村は、料理を味わう場所じゃなく、“人の温度”を感じる場所なんです。」
では、常連たちと自然に打ち解けるためにはどうすればいいのでしょうか?
ヒデさんが実践している3つのポイントがあります。
①「聞き役」になること
屋台では自分の話をするより、まず店主や常連の話を聞くことが大切。
地元の話題、祭り、名物料理の由来などを聞くだけで、一気に距離が縮まります。
特に「この料理って地元の人も食べますか?」と尋ねると、会話が弾むきっかけに。
②「ありがとう」を口にすること
屋台村では、料理やお酒だけでなく“心配り”にありがとうを伝えることが重要です。
ヒデさんは、どんなに忙しい店でも、
「おいしかったです。ごちそうさまでした。」
の一言を欠かさないそうです。
その一言が、次の出会いの“扉”を開くのです。
③「2軒目」で本音の会話が生まれる
一軒目ではまだ緊張していても、2軒目になると不思議と打ち解けてくるのが屋台村の醍醐味。
「さっきの店で会いましたね!」という偶然の再会から、
自然と乾杯が始まることも少なくありません。
ヒデさんはそれを「屋台村マジック」と呼びます。
また、常連との交流はSNSでも続くことが多く、
「次に行くとき連絡して」「あの人まだ元気?」といった温かいやり取りが生まれます。
ヒデさんも「屋台村でできた友人は、もう100人を超えた」と話しており、
それが彼の旅を支える“絆”になっています。
ヒデさんは最後にこう語ります。
「屋台村は一期一会の連続。でも、その一瞬を大切にすれば、
どんな街でも“第二の故郷”になるんです。」
お酒が苦手でも、人が好きなら楽しめる。
それが屋台村の魅力であり、ヒデさんが全国を巡る理由でもあるのです。
マツコの知らない世界 屋台村の世界 ヒデさんとは?全国を巡る魅力を総括
ここまで、マツコの知らない世界で紹介された「屋台村の世界」と、
その魅力を全国1000軒以上巡ってきたヒデさんの視点から深く掘り下げてきました。
ヒデさんの旅は、ただの“食べ歩き”ではありません。
それは、人と人をつなぐ“心の旅”。
屋台村の暖簾をくぐるたびに、新しい出会いがあり、笑顔があり、物語が生まれます。
ヒデさんが伝えたいのは、「屋台村は地域の魂」だということ。
一軒一軒に店主の人生があり、
その味や言葉、空気が訪れる人の心を温めるのです。
この記事のポイントをまとめると——
最後に、ヒデさんの言葉をもう一度。
「屋台村は、人生をちょっと明るくしてくれる魔法の場所。
知らない街で、知らない人と笑い合う瞬間が、
一番人間らしいと思うんです。」
マツコの知らない世界で伝わった“屋台村の世界”。
その扉を開くのは、あなたのちょっとした好奇心かもしれません。
次の夜、勇気を出して、屋台の暖簾をくぐってみませんか?
――そこには、きっと忘れられない出会いが待っています。
広告
【じゃらん】国内25,000軒の宿をネットで予約OK!2%ポイント還元!広告
実名口コミグルメサービスNO.1【Retty】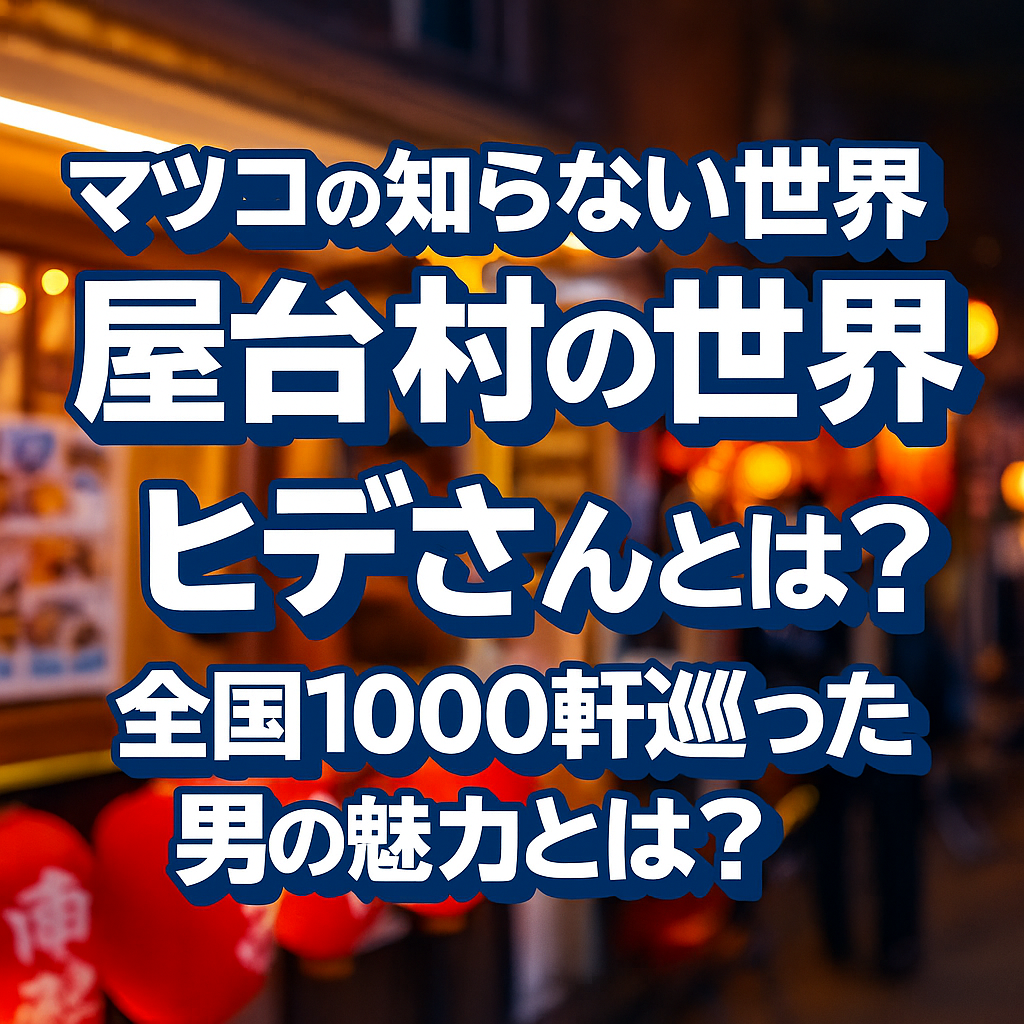

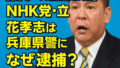
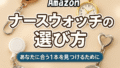
コメント